
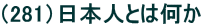
今回は、評論家加藤周一《大正8年(1919-平成20年(2008)》著「日本人とは何か」講談社学術文庫の中の、私なりに関心が持てたほんのさわり部分の抜粋を取り上げて、以下に記載して感想を述べてみる。
この本は、日本人論八篇を収録しているが、初版が昭和51年だから既に38年前だが、決して古さを感じない。日本人のありようの普遍性を追求しているから興味は尽きない。
◎日本人とは何か
ーたとえば長い歴史を顧みて、日本人は音楽家であるよりむしろ美術家であったと言えそうである。美術家としての日本人は、絵画・彫刻・建築・造園・また各種の工芸のあらゆる領域にわたって、中国の強い影響を受けながらも、独特の境地をひらき、固有の様式を洗練した。ー
確かに、一例として浮世絵が世界に与えた影響は多大だが、音楽においてこれといって世界に多大な影響を与えたことはあまり記憶にない。
◎外から見た日本
ー1964年「オリンピック」まえの東京に帰ってきていまさらおどろいたことは、東京都の進取の気象に富み、未来を望んで過去をかえりみない果敢な態度である。未来とは、いうまでもなく高速道路の便利で実用的で無格好で巨大なコンクリート構造であり、過去とは遠くは江戸以来近くは明治以来の日本橋の風情や赤坂見附から三宅坂へかけて堀と石がけと弁慶橋の作る美的調和である。前者によって後者をぶち壊すことにこれほど決然たる都会は、少なくとも古い大都会の中で、おそらく例がないだろう。パリはコンコルドの真ん中に高速道路を通すことを夢想さえしないだろうと思う。ー
たぶん建築物に対する石の文化と木の文化の違いが如実に出た例だろうが、形あるものは無くなるというDNAが日本人の体質に刷り込まれて簡単には消えない。私も旅をしていて、もし昔の風情がそこに残されていたらという場所に幾度も遭遇しているのだが。
◎天皇制について
ー無条件降伏したその日から、万事が変わったことは周知のとおりである。占領軍は信じられてきた価値の 秩序を揺り動かし、その中心に一撃を与えた。占領は夏に始まったから、開襟シャツの司令官がフロックコートの天皇と並んで写真を撮り、それを新聞雑誌に発表した。米国の営利雑誌はその下に注釈して「もと神」と書いたのである。日本側では注釈を翻訳する時に、もとの表現の辛辣な諧謔味をとり除いた。そこには、開襟シャツの大柄な外国人とその傍らに立っている昨日までの「御真影」とを対照させた写真に対する、日本側の困惑がよく表れていた。しかし、おそらく天皇のために怒る者は殆どいなかったし、昔の臣民の中で、何らかの激しい反発を表明するものもいなかった。反応は驚くほど穏やかであった。ー
秩序を揺り動かし、その中心に一撃を与えた。占領は夏に始まったから、開襟シャツの司令官がフロックコートの天皇と並んで写真を撮り、それを新聞雑誌に発表した。米国の営利雑誌はその下に注釈して「もと神」と書いたのである。日本側では注釈を翻訳する時に、もとの表現の辛辣な諧謔味をとり除いた。そこには、開襟シャツの大柄な外国人とその傍らに立っている昨日までの「御真影」とを対照させた写真に対する、日本側の困惑がよく表れていた。しかし、おそらく天皇のために怒る者は殆どいなかったし、昔の臣民の中で、何らかの激しい反発を表明するものもいなかった。反応は驚くほど穏やかであった。ー
その後話は、穏やかだからといってなんの反応も日本人が示さなかったというのではないと続く。
それにしても右の写真はショッキングである。一国のリーダー同士で敗者と勝者がこれほどはっきり表された写真もあまり見ない。片や敗者はフロックコートの正装で直立不動の姿勢、一方勝者は普段着の開襟シャツで腰に手を当てて見方によればふんぞり返っている。この立場がまるで反対だったら、天皇は腰に手を当て普段着で敵将に相対したであろうか。結論は否で、武士の情けを持って敗者に接したと思うのだが。
それはさておき、あの敗戦で一夜にして価値観がまるでひっくり返ってしまったときの日本人態度は周知のとおりであるが、それもまた日本人が持つ特性である。
ここで俳人吉田類の「昭和の日あの閃光の真っ二つ」という名句をを思い出した。
同じく天皇制についての中で、
ーきだみのる氏は「部落に宗教はない。宗教の屍(しかばね)があるだけだ」と断定し、次のような注目すべき観察をした。それは村のお彼岸会があり、檀家たちがお経をきき、読経料200円ずつを出した後で、きだみのる氏が住職や総代たちと酒を飲んだ時に考えたことである。「彼岸の今日の儀式、費用、それらすべて今日の部落の生活の現実に対して何の意味を持ってはいない。住職も部落の連中も懲罰の場としての地獄も亡霊の存在も信じてはいない。住職は生活のためそれを信じている振りをしているかもしれない。しかも他のものは全く意味を持たない伝統の歯車のまにまにこのような儀式を行っているのだ。と(中略)外からの観察者(外国人)にとっては、田舎に宗教が見え、うちからの観察者にとっては宗教の屍がみえる。ということは田舎には都会よりも、宗教殊にその宗教ではなく、その儀式的な面がよく保存されているということなのであろう。「住職は生活のためにそれを信じている振りをしているかもしれない。」ーときだみのる氏はいう。それを見破るためには、氏のように長い間部落に住み込む必要があるだろう。調査表を配布して、回答を集めるやり方で、それを見破るのは難しい。ー
この話は天皇制についてではないが、実に日本人の宗教観が出た話だと思う。
◎戦争と知識人
ー日本の知識人がみな永井荷風であっても、ファッシズムをどうすることもできない。しかし実情は知識人の大部分が、荷風でさえなかったのだ、つまり食い止めることをはっきり望んでさえいなかったのである。ー
荷風は知られた反戦論者だが、概(おおむ)ねの知識人は漠然と戦争に望んでいたということであろ。
一方興味あるのは宗教団体特にキリスト教徒の戦争に臨む態度は、
ー例えばキリスト教徒は当然「神」を天皇の上に置いたはずであり、その心理の超越性を信じていたはずである。しかしすでに昭和十二年(1973)に、東京YMCAは「正義の皇軍を護り、支那の為政者の目を開かしめ給え」と祈り、聖公会は十三年に「信徒の間に、国体観念の明徴、尽忠報国の念の伸長を祈る。今次事変の聖戦なりとの確信再認識」を唱えていた。(中略)しかしここでも自由な批判的精神は、組織の外に生きていた。矢内原忠雄(1893-1961)は、経済学者として、インドの英国植民地主義、台湾での日本植民地主義を研究し、批判していたが、キリスト信者としては、講演して「日本の理想を生かすために、一先ずこの国を葬って下さい」とまでいったという。ー
概ね日本人キリスト教徒知識人も戦争に賛成しているようだが、中には矢内原のように「一先ずこの国をほ葬って下さい」と反戦を唱える、しっかりとした知識人が存在したことも確認できる。
話はもっと多岐に渡っているのでもっとたくさんの話を載せたいが、長くなるのでここで終わらせることにする。ほんの触りだけになってしまったことをお詫び申し上げ、日本人のなんたるかが少しでも感じてもらえればと思う次第です。
(完)
平成 27年 1月 1日 DOKKOU著
秩序を揺り動かし、その中心に一撃を与えた。占領は夏に始まったから、開襟シャツの司令官がフロックコートの天皇と並んで写真を撮り、それを新聞雑誌に発表した。米国の営利雑誌はその下に注釈して「もと神」と書いたのである。日本側では注釈を翻訳する時に、もとの表現の辛辣な諧謔味をとり除いた。そこには、開襟シャツの大柄な外国人とその傍らに立っている昨日までの「御真影」とを対照させた写真に対する、日本側の困惑がよく表れていた。しかし、おそらく天皇のために怒る者は殆どいなかったし、昔の臣民の中で、何らかの激しい反発を表明するものもいなかった。反応は驚くほど穏やかであった。ー